
子どもに「やれ」と強制しない、「やりたい」と思うまで気長に待つ──現役プログラマープロさんの子育て方法
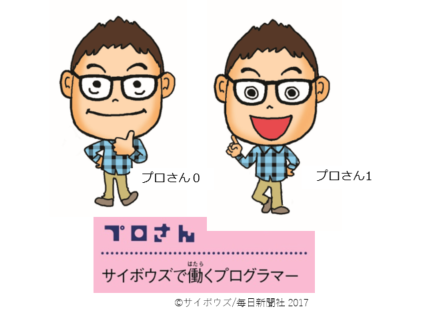
-
Target この記事の主なターゲット
-
- プログラミングに興味のある親
- 子育てに関心のある人
- IT教育を考えている教育者
- プログラマーを目指す学生
-
Point この記事を読んで得られる知識
-
この記事を通じて得られる知識として、まず、子どもに対する適切な教育アプローチが挙げられます。子どもに「やれ」と強制するのではなく、彼らが「やりたい」と思うまで気長に待つことの重要性について語られています。プロさん0とプロさん1の子供時代のエピソードを通して、自然とプログラミングに興味を持ち始める過程が紹介されています。
また、子育てにおいて、子どもがあることに興味を持ったときにあえて少しやらせて止めることで、長期的な興味を促進する方法も述べられています。この方法により、子どもは持続的に興味を抱き続ける傾向があると説明されています。
さらに、プログラミングが持つ魅力について、プログラムを通して自分のアイデアを形にし、自ら試せる喜びや学びがあります。これが、プロさんが子どもにプログラミングを学ばせたい理由の一つです。プログラミングを通して、自己表現の手段を持つことの楽しさも伝えることができます。
-
Text AI要約の元文章
-
子どもに「やれ」と強制しない、「やりたい」と思うまで気長に待つ──現役プログラマープロさんの子育て方法
サイボウズのプログラマーの"プロさん"に、コンピューターやプログラミングについて聞くシリーズ「プログラミングって?」。記事を作るにあたってお話を聞いているプログラマーは2人、つまりプロさんは実は2人います。
今回は番外編として、プロさんがどんな子ども時代を過ごしたのか、そして子育てではどんなことに気をつけているか、聞いてみました。プロさんは実は2人いる。プログラムは0と1でできているから、プロさん0とプロさん1にしてみたよ。
ゲーム機がないから家のパソコンで遊んでいた
いつも子どもたちに講義をしてもらっているプロさんですが、今日はご自身のことや子育てについて伺ってみたいと思います。まずはご自身のことから。プロさん0は子どもの頃はどんなお子さんだったんですか?
家にはゲーム機が無く、似たようなもので家にあったのは、ネットにつながっていない父親のパソコンでした。使い方が書いてあるマニュアルがあって、そこにプログラムの仕方も書いてあり、それを読みながら遊んでるうちに、自然とプログラムができるようになっていったという感じでした。
もう1人のプロさん(プロさん1)はいかがでしょう?
家にゲーム機がないのは私も同じで、友達がゲームをしているのを横で見る係でした(笑)。横で見ていて、盛り上げたりアドバイスしたりしていました。
小学4年生のころから父親がもらってきたパソコンを触りはじめて、それが私にとってのゲーム機の代わりになりました。ほとんどの時間はプログラミングをしていたんだけど、親はそれを理解できなくて、ゲームばかりしていると思っていたようです。 あとは鉄道模型が好きでプラレールは今でも好きです。あまり今の子どもと変わらないんじゃないかな(笑)。興味がわかない時期に教えるのは親の時間の無駄
プロさん1は子どもを育てるうえで、気をつけていることはありますか?
何事も強制しないようにしています。子どもに限らず大人もそうですが、「やれ」と言われたらやりたくなくなります。逆に、やりたいと思ったら人は自然にどんどんやり始めると思っているから、何事も子どもが「やりたい」と思うまで待つようにしています。きっかけを小出しにしつつ待っていれば、必ずその時は来ます。
確かに、大人でも「やりなさい」と言われるとやりたくなくなりますね。
そうだと思います。その分、自分が子どもに「やらせたいなー」と思ったことをやり始めたら、やった!と思います。でも、そのまま思う存分やらせることはなくて、ちょっとやったら、あえて止めます(笑)。
え!? それはなぜですか??
大人が止めると「えー、もっとやりたいのに!」と子どもは思うようです。その経験があったことで、その日限りではなく、1週間、1ヶ月、それ以上と興味を持つ時間が続くようになりました。
あれこれ工夫しても、なかなか興味を持ってもらえないことはあります。いや、「よく」あります(笑)。その時は、"興味がわかない時期は、そこに親が時間をかけても時間の無駄"と思い、とにかく気長に待つようにしています。焦ってもいい結果にはならなかったので……。プログラミングの楽しさは教えたい
やはりプログラマーとして子どもにもプログラミングを教えたいという気持ちはありますか?
自分がプログラミングに興味を持ったのが小学生のときだったので、小学生のどこかの時点では教えようと思っています。子どもが「できること」の選択肢にプログラミングを持っておいてほしいという気持ちはあります。
プログラミングができると何が違うのでしょう?
プログラムが書けると、自分の考えを自分だけで試すことができます。それにより、自分のアイデアをどんどん磨いていけるのです。
"くだらない自分のアイデアもまずは自分で形にできる"というのが楽しいです。つくるのが楽しいから、その楽しさを分かってほしいという気持ちもあります。そうなるといいな(笑)。2016年6月28日サイボウズの青野社長が考える「子どものIT教育」──必要なのは言語の習得ではなく「問題を考える力」 2015年8月11日「外で遊ぼう」「人との対話が大事」なんて子どもにとって余計なお世話──実践子どもIT教育 2015年7月31日 プログラマーって何しているの? IT企業の中身はどうなっているの? 中学生が聞いてみた タグ一覧
- サイボウズ
- プログラミング
- プログラミング教育
SNSシェア
- シェア
- Tweet



