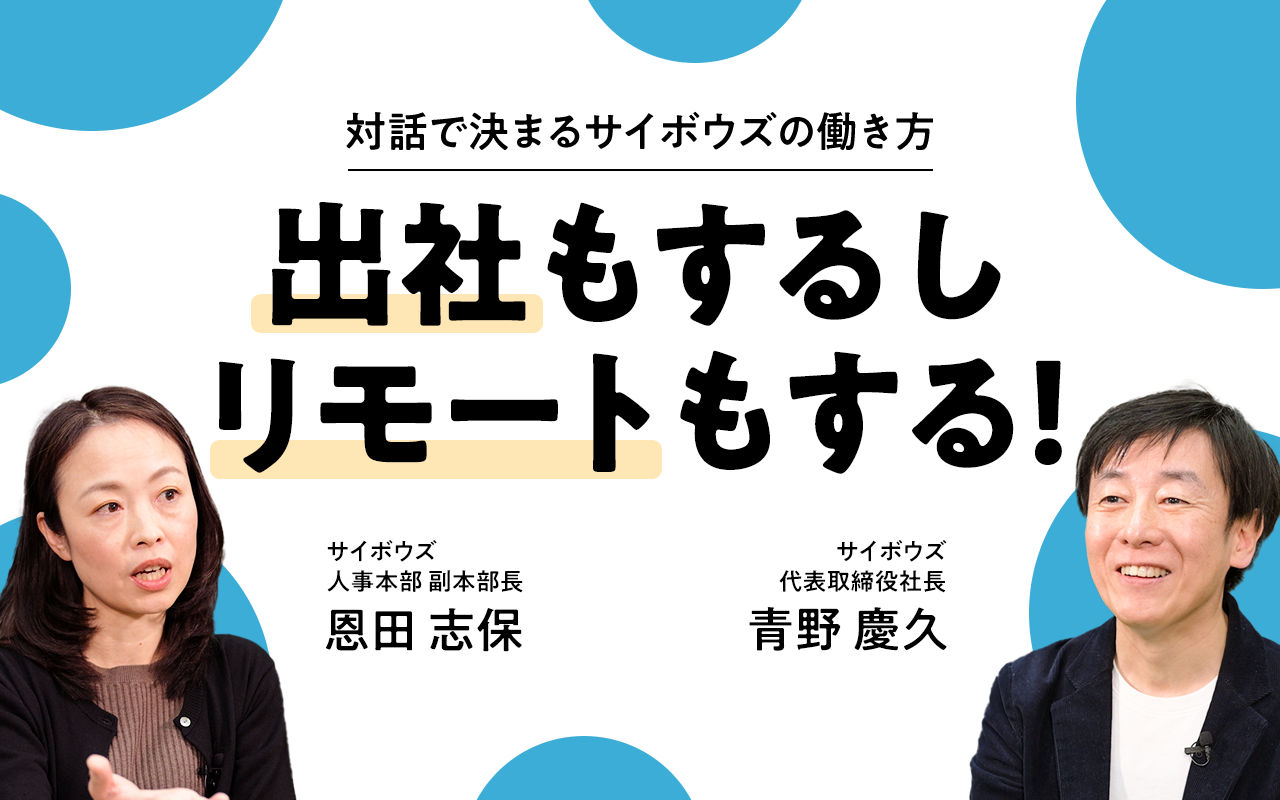出社かリモートか、結局どっちが正解なの……?
「自分はリモートじゃなければ困る」と訴えるメンバー。「成果を出すために出社してほしい」と要請する経営者やマネージャー。多くの企業でくり返される二項対立の議論に、ちょっと疲れてしまった人も多いのではないでしょうか。
サイボウズは「働く人が幸せで、チームの生産性を高められるなら、手段はどちらでもいい」と考えています。
みんなが納得でき、幸福度も生産性も高まる働き方を実現するために欠かせないプロセスとは? サイボウズ代表の青野慶久と、人事本部 副本部長の恩田志保が議論します。
「リモートワークで生産性が下がる」は本当?
コロナ禍の収束以降、それまでリモートワークを進めていた企業でも、会社方針として出社を義務化する動きが目立つようになりました。
リモートワークが好きな人にとっては大変ですね。サイボウズはどんな状況なんでしょうか?
2024年10月の調べでは、1か月あたりの平均出社率が約2割でした。サイボウズでは「週1回出社」が平均ということですね。一方、「月に1回も出社していない」人も約2割にのぼります。
サイボウズでは相変わらずリモート派が圧倒的多数ですが、出社回帰する企業や職場では「リモートワークは生産性が下がってしまう」と考える人も多いようです。
「リモート=生産性が下がる」と決めつけるのは、ちょっと乱暴な気もします。
下がる人は下がるし、上がる人は上がるというだけではないでしょうか。仕事内容や本人のコンディションも影響するでしょう。
ちなみに僕自身は「リモートで生産性が上がる」と感じていますよ。移動時間がないため疲れにくく、1日の中で集中できる時間も増えました。
一方で、「やっぱり自分は出社したほうがやりやすい」と考える人もいると思うんです。その人にとっては出社が正解なんですよね。
出社なのかリモートなのか。僕は、それぞれの企業にそれぞれの方針があっていいと思います。
ただ経営者として気になるのは、どんなプロセスでその決定に至ったのかということ。
メンバーと対話しながら納得のいく結論に至ったのならいいけど、誰かが思いつきで決めているだけなら、会社もメンバーも不幸になってしまう可能性が高いでしょう。
青野慶久 (あおの・よしひさ)。サイボウズ代表取締役社長。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パナソニック)を経て、1997年サイボウズを設立。2005年現職に就任。著書に『チームのことだけ、考えた。』(ダイヤモンド社)、『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。』(PHP研究所)など
マネージャーとメンバーによる「100人100通りのマッチング」
サイボウズでも、コロナが収束して間もない時期には、働き方に関する認識がマネージャーとメンバーで異なっていたことがありましたよね。
はい。そのため2024年8月に、全社員に対して働く場所とチームへの貢献度をマッチングする「100人100通りのマッチング」(※)という取り組みを進めました。
まずチーム内で働き方を話し合い、「チームの働き方ポリシー」を決めます。
マネージャーは、メンバーにどんなふうにチームに貢献しようと思っているのか、業務をどのように進めて成果を出そうと思っているのかを聞いていき、オファーを出してマッチングしていきました。
プロ野球選手が一斉に契約更改するように、本当に全員が希望を出しましたよね。
マネージャー陣は、メンバーのさまざまな希望を受け止めて調整するのに苦労したかもしれませんね。
マッチングのプロセスでは、最初にマネージャーが「わたしたちのミッションはこれだから、達成のためには週1回くらい出社することが望ましいと思っている」といったポリシーを伝えます。
メンバーはそれを踏まえて自分の働き方を考えるので、必然的にチームの目線を持つようになるんですよね。
※サイボウズは2024年、それまで象徴的に発信してきた「100人100通りの働き方」という表現を見直し、「100人100通りのマッチング」に変更した。個人が希望する働き方や出せるアウトプットと、チームが求められる役割が合致した場合にマッチングが成立する。
恩田 志保(おんだ・しほ)。サイボウズ 人事本部 副本部長。2007年にサイボウズに入社し、一貫して人事領域に従事。現在は副本部長として、人事戦略、働き方、環境デザインなどに幅広く携わる
制度は全員の対話で決める。「賛成多数だからGO!」ではない
サイボウズでは働く場所以外にも、制度や仕組みをつくるときには必ず、起案者が説明責任を果たせる結論が出るまで議論しながら決めています。
しょっちゅうバトルが起きていますよね(笑)
コロナ禍に支給していた「在宅勤務手当」を廃止する際も、人事は大変な思いをしたんじゃないですか?
「在宅勤務の推奨期間が終わったので、手当をなくそうと考えています」と発信したところ、たくさんの賛成・反対の意見が寄せられました。
経営会議で起案された「在宅勤務手当の廃止」の議題に対する助言の一部。承認までに70件以上の助言が集まった。助言はkintoneで誰でも登録・閲覧できるようになっている。(画像は編集部にて一部抜粋・編集したものです)
炎上寸前の社内議論を経て、最終的には目的を見直し、いまのわたしたちに必要な手当を定めて運用しています。
こうしたプロセスはたしかに苦労の連続です。
それでも、オープンに議論することで最終的な結論への納得感が高まりますし、人事部門内にも新たな気づきがもたらされるので、わたしたちに欠かせないプロセスだと感じています。
「人事の発案に賛成多数だからGO!」という単純な話ではないんですよね。
極端なことを言うと、賛成99の反対1という状況でも、反対1を尊重することがありますから。
はい。賛成・反対のそれぞれの背景を見てコミュニケーションを取り、多数決ではなく、理想を踏まえて社内に説明できるかたちで結論を出しています。
これは本当に大変なことだと思いますよ。
人事が提案する内容は多くの人に影響します。そのため猛烈な批判を浴び、原案が完全に消えてしまう場面を何回も見てきました。
面倒な対話プロセスを経ることこそ「最強のやり方」
このやり方は面倒に見えますが、実はもっとも効率的だと思っています。たくさんの意見を集め、もっとも良い案にたどり着けるからです。
みんながオープンに議論して結論にたどり着くので、決めた後の運用スピードも非常に速いんですよね。
ただ、議論の過程では反対意見を多く目にするので、起案者のメンタル的にはしんどい部分もあります。日本人はこれを嫌がる傾向があるのかもしれません。
わたしも「できるだけ反対意見が出ないよう、穴がない資料を作らなきゃ」と考えていた時期があります。
でも実際にやってみると、むしろ穴がある案のほうが議論が深まるんですよね。
そうなんですよ! このやり方のコツは、起案者自身も結論を持っていないタイミングで案を出すことにあります。
具体的な案を出さずに「リモートワークの生産性、何となく下がっていませんか?」とゆるめに問いかけるくらいでいい。そうすると共感する人もしない人も反応してくれて、多方面にアイデアが集まります。
僕は、事業戦略を練るときにもこの技を使って、社内にゆるく問いかけていますよ。
面倒に見えるけど、実はもっとも効率的。全社員と行った「100人100通りのマッチング」 も同じですね。
はい。
一人ひとりが自分の働き方を主体的に考え、マネージャーと議論し、チームの理想像とマッチングされているわけですから、僕は最強のやり方だと思います。
働く個人のモチベーションも爆上がりするかもしれません。
そういえば、働く場所の再マッチングを実施した後、社内では人事への感謝の声が寄せられたんです。
「2024年の人事施策の中でもっともうれしかった」「マネージャーと本質的な会話ができるようになった」と言ってくれる人もいました。
これまでは「自分だけがわがままを言っているのかも……」と後ろめたく感じている人がいたのかもしれませんね。
チームの理想像を議論し、マネージャーもメンバーも納得した上で働く場所を決めたからこそ、そうした後ろめたさがなくなったのではないでしょうか。
出社とリモート、それぞれに捨てがたいメリットがある
そうやって一人ひとりが理想の働き方を考えることで、リモートと出社、双方のメリットが改めて見えてきたように思います。
はい。リモートの場合は交換できる情報がテキストや音声、動画に限られてしまいます。オフィスに来たほうが情報伝達効率が上がったり、新たなつながりができたりすることも事実です。
サイボウズでも出社の意義を見直す動きがでてきました。たとえばマネージャー陣は「リアル合宿」を復活させています。
背景には、組織規模が拡大しマネージャーの人数が増えたことで、複数の本部を横断する議論や意思決定が進みにくくなったことがあります。
そこでリアル合宿を復活させたところ、たった1日でもたくさんのことを決められるようになりました。
新入社員のオンボーディングでもリアルが重要だと感じています。特に入社当初の関係性をつくる段階ではリアルに集まる機会が欠かせません。
一方ではリモートの情報共有のほうが圧倒的に速い場合もありますよね。
サイボウズではグループウェア上にありとあらゆる情報が集まるので、出社して誰かに聞きに行くよりも、グループウェアを検索したほうがほしい情報に速くたどり着けます。
わたしはグループウェア上で運用している「分報」(※)に助けられていますね。青野さんも雑談っぽく、いろいろなことを発信していますよね。
わたしたちからすると、そうしたつぶやきは「いつでも社長の考えていることがわかる」という意味で貴重なんですよ。
出社していても、広いオフィスの中で青野さんと出会う確率は低いですし、いつでも雑談できるわけではありませんから。
出社にもリモートにも、それぞれ捨てがたいメリットがあるということですよね。
どちらか一方が正解ではない。その時々の目的に応じて、手段を使い分けることが正解なのだと思います。
※分報とは、業務の状況やいま考えていること、雑談などをリアルタイムにオンラインで発信してチームに共有する取り組みのこと。「社内SNS」「社内X」のようなイメージ。
「個人の幸福」を本気でリクエストすれば「生産性の向上」につながる
わたしはもうひとつ、「出社かリモートか」の議論を見ていてどうしても気になることがあるんです。
働く場所を決めることは、個人の幸福にもチームの生産性にも大きな影響を与えると思います。でも実際の議論では、幸福か生産性か、どちらか一方に偏っていることが多いのではないでしょうか。
たしかに。個人の幸福だけを考えていてもチームの生産性はあがりませんよね。
かといって、チームの生産性をあげることばかり考え、個人の幸福に目を向けないでいると、結果的にチームとしての成果を出せないかもしれません。
「自分は仕事とプライベートを切り分け、出社して思いきり働きたい」と考えている人にリモートを押しつけても、その人は不幸になってしまうだけ。モチベーションが低下し、結果的にチームに悪影響を与えてしまうかもしれませんね。
現在の僕でいうと、もし出社を押しつけられたら間違いなく不幸になります。
自宅の冷蔵庫に1.5Lのコーラを常備し、キンキンに冷えた状態でいつでも飲めることにこの上ない幸せを感じているので(笑)
何をもって幸福を感じられるのかは、本当に100人100通りなんですよね。働く本人も、自分自身の幸福についてしっかり考えるべきでしょう。
みんなが幸せに働き、「ここにいてよかった」と思える状態になれば、当然生産性も上がっていくはず。
そうした好循環をつくるために、まず自分自身の幸福と向き合い、ちゃんと言葉にして伝えることが大切なのだと思います。
メンバーは「言わなきゃダメ」だし、マネージャーは「聞き出さなきゃ負け」。
その際には、勤務条件や給与などの表面的・定量的な条件だけではなく、互いの背景もちゃんと知っておくべきだと思います。
あるメンバーについて、「この人は関西出身でゆくゆくは地元に帰りたいと思っている」とマネージャーが理解していれば、関西で人材を求めているチームにうまくマッチングできるかもしれませんよね。
たしかに。「出社かリモートか」といった手段に関する会話だけでは実現できないマッチングですね。
はい。逆にマネージャーから「5年後にはチームをこんな状態を実現したい」という思いを伝えていれば、メンバーがそれに共感して、当初は考えていなかった働き方を受け入れてくれるかもしれません。
個々に対話を重ね、本気でリクエストし合う。そんな関わり方を大切にするチームでありたいですね。
執筆:多田慎介 撮影:高橋 団(サイボウズ)企画・編集:山本悠子(サイボウズ)
2024年10月29日
サイボウズは「100人100通りの働き方」をやめます。社員数1000人を超えても、成長と幸福を両立させるための挑戦
2022年2月9日
まるで社内SNS!「分報」でメンバーの状況をハイブリッドワークでも感じられるようにしよう