
多様なチームが加速させる、未来のモビリティづくり
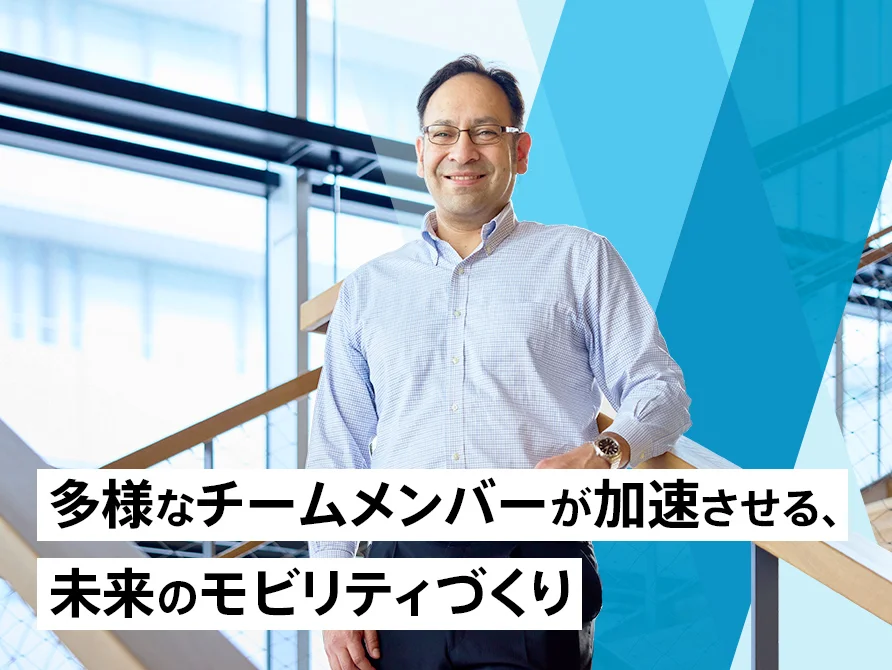
-
Target この記事の主なターゲット
-
- 技術者
- エンジニア学生
- 自動車業界関係者
- ソフトウェア開発者
- 企業の人材育成担当者
-
Point この記事を読んで得られる知識
-
この記事を読むことで、現代のモビリティ業界でソフトウェアの役割がますます重要になっている点を理解できます。特に、ソフトウェア定義型自動車(SDV)という新たな概念が台頭し、これが従来の自動車開発に対する大きなパラダイムシフトをもたらしていることが強調されています。SDVは、車両機能の更新がソフトウェアのアップデートを通じて実現される自動車のことで、これに伴いソフトウェアの開発がますます重要となり、業界内でのソフトウェアエンジニアの需要が急速に高まっています。
また、デンソーの強みとして、In-CarとOut-Carをつなぐインターフェース設計の重要性が挙げられています。グローバルなソフトウェア開発体制を構築し、各地で効率的かつ迅速な開発が可能なシステムを確立している点も紹介されています。カルロスさんの経験を通じて、異文化理解の重要性や、多様なバックグラウンドを持つメンバーと協働する際の心構えも学べます。
さらに、ソフトウェアエンジニアとして求められる能力として、柔軟な適応力、モチベーション、コミュニケーション能力の重要性が述べられています。技術革新のスピードが非常に速い現代においては、日々更新を続ける姿勢が求められていることが強調されています。最後に、エンジニアとしての夢や誇りを大切にし、ものづくりへの情熱を持ち続けることが次世代のエンジニアへのメッセージとして伝えられています。
-
Text AI要約の元文章
-
2025.7.9
キャリア・生き方多様なチームが加速させる、未来のモビリティづくり
グローバルなソフトウェア開発体制によるSDVへの挑戦
この記事の目次
いまモビリティ開発においてソフトウェアの重要性が高まっています。デンソーでは「ソフトウェア改革統括室」を立ち上げ、新しいモビリティの価値創造に挑戦中。そんな転換期を支えるソフトウェアエンジニアたちは、どのようなチームで、どのような働き方をしているのでしょうか。今回は、研究者として医療用の機器やロボティクス・画像処理などの最先端技術開発の経験を経て、デンソーにて車体機能を制御するコンピューターのソフトウェア開発に携わるテルセロ・カルロスの取り組みを紹介します。
この記事の目次
モビリティ業界の変革期を支える、ソフトウェアエンジニア
──近年、「ソフトウェア定義型自動車(Software Defined Vehicle、以下SDV)」が注目を集めていると思います。なぜ、モビリティの領域においてソフトウェア開発の重要性が高まっているのかについて教えていただけますか。
まず、SDVというのは、その名の通りソフトウェアを中核に据えて設計されたクルマのことです。車両の機能がソフトウェアのアップデートによって更新されることを前提に開発されていますので、「スマートフォンのような自動車」と言われることも多いですね。
従来の自動車は主にハードウェアの性能改善に注力してきましたが、SDVでは、無線通信を経由してデータを送受信するOTA(Over the Air)技術を活用して車載ソフトウェアを更新することが前提になり、運転支援機能や航続距離の改善といったことがソフトウェアのアップデートのみで実現できるんです。こうした大きなパラダイムシフトによって、モビリティ業界そのものが変わろうとしていると感じています。
モビリティに接続されるシステムが増えれば、それを支えるソフトウェアやプラットフォームもおのずと増えていきます。これからのソフトウェアエンジニアは、SDVや自律走行といったトレンドに対応する必要があり、従来の組み込みエンジニア以外にもソフトウェアの領域が広がっているのが現状です。
車種ごとにソフトウェアの数が増え、AIやバーチャルECUの活用、開発プロセスを自動化する新しいツールの導入が必須となるなかで、業界のなかでのソフトウェアエンジニアへの需要は、現状のエンジニア人口を上回るペースで増加しているんです。
──そのような環境のなかで、デンソーの強みはどこにあるのでしょうか。
私たちデンソーがとくに注力しているのは、In-CarとOut-Carをつなぐ「界面」の設計です。車載ソフトウェアでは、パワートレインやボディ制御など車両内部のシステム(In-Car)と、クラウドやモバイル技術(Out-Car)をどう効果的に連携させるかが非常に大きなテーマになります。
デンソーでは、組み込みソフトウェアから大規模統合系ソフトウェアに至るまで、40年以上にわたって培ってきた技術があります。その進化は、デンソー独自の「カイゼン」と「品質」を追求する文化に支えられてきました。これまでの技術を活かして、In-CarとOut-Carを円滑につなぐための標準化や統合制御システム開発、セキュリティリスクへの対応など、新たな課題に取り組んでいます。
また、グローバルな開発体制の構築も同時に進めていて、各地の開発拠点で仮想ECU技術を活用しながら効率的にソフトウェアを開発し、最終的には実機(ハードウェア)検証までしっかり行えるようにしています。それに加えて、世界中のチームと連携しながら、お客様と緊密なコミュニケーションを取り、効率的に製品を開発できるのも強みです。
アカデミアを飛び出し、市場での可能性を追求
──カルロスさんご自身はもともとアカデミアでご活躍されていたと伺いました。なぜ自動車のソフトウェア開発の道に進まれたのでしょうか?
私はグアテマラ出身で、2004年に来日して名古屋大学でマイクロ・ナノシステム工学を学び、博士号を取得しました。専門はマイクロ・ナノロボティクスで、研究員や特任講師として約8年、医療用ロボティクスや画像処理、医療機器などの最先端技術開発に携わってきたんです。
研究の道は非常に面白かったんですが、産業の現場で自分のアイデアや設計を実際の製品として市場に届けたいという思いが強くなりました。デンソーならそれが実現できるのではないかと考え、2012年に入社したんです。
実際に、自動車向けの組み込みソフトウェア開発をする上で、少人数の研究チームで多様な工程を自分でこなしてきた経験はすごく活きています。ロボット開発では、ECU開発と同じく、組み込みソフトウェアを利用します。制御するコンポーネントは違えど、利用する技術には似ている部分があるんですよね。「ロボットをつくる代わりにECUをつくる」という感じで、応用分野が変わっただけというイメージです。
──カルロスさんはデンソーへの入社後、世界中の自動車メーカー向けのエアコンパネルやボディECU、車体機能を制御するコンピューターのソフトウェア開発などに携わってこられましたが、これまで担当されていたプロジェクトのなかで特に印象深かった出来事はありますか?
そうですね。私がミシガン州にいたときに、新型コロナウイルスに伴う数カ月間のロックダウンがありました。顧客からサプライヤーである私たちに対し、「遅延が発生しない」ように依頼があり、開発スケジュールを最適化する必要がありました。そこで、新しいコミュニケーションツールを導入し、小型ベンチ・自動化評価環境を開発することで、在宅勤務はもちろん、時差に関係なく効率的に業務を進められる体制を構築したんです。ロックダウン解除後も効率的かつ柔軟な働き方は継続されています。
異文化を理解する、チームでの働き方
──先ほどグローバルネットワークのお話もありましたが、改めてデンソーのチームの強みについて教えてください。
やはりデンソーの強みのひとつは「世界規模のネットワーク」だと思っています。例えばアメリカのお客様がいればデトロイトのオフィスで直接会議ができるし、それはヨーロッパでもアジアでも同様です。そうしたグローバルな開発体制を支える拠点として、日本のデンソー本社が世界各国のチームに技術移転やサポートを行うんですね。顧客に近い場所で開発を進めるのが最良の戦略ですが、そこに必要な知識や経験を集めて提供するのがデンソー本社の役割になります。
100人を超えるチームでソフトウェアを開発するのは、オーケストラを指揮するような感覚に近いと私は思っています。全員が正しく演奏(=作業)できるように、演奏内容を聴き分けて調整しなければならない。しかし「こうやれ」と指示するだけではうまくいかないことも多いので、チームメンバーのアイデアを支えながらプロジェクトのゴールに導くのがマネージャーとしての私の役目ですね。チームにある程度の自由と権限を与えることで、多くのアイデアが生まれるんです。
──チームのなかには、多様な国籍やバックグラウンドの方がいらっしゃると思います。そうした方々と仕事を進める上で大切にしていることは何でしょうか?
そうですね。私のチームにはフランスやスウェーデン、中国など、多様なバックグラウンドをもつメンバーがいます。文化の違いを理解し尊重しながら進めるのは大変ですが、とても刺激的です。その際に心がけているのは、「この国の人はこのような振る舞いをする」というレッテルを貼らないことです。異なる文化圏のメンバーを理解し、ともに仕事をする上ではオープンマインドであることが欠かせないんです。また、それは製品開発においても同様です。多様なメンバーが在籍しているからこそ、各国・地域の社会課題やニーズに応じた開発が可能になると考えています。
日々変わる技術を前にして、求められるマインドセットと夢
──カルロスさんが考える、これからのソフトウェアエンジニアの役割についても教えていただけますか?
最初に申し上げたように、いまソフトウェアエンジニアに求められるスキルの幅は広がっています。だからこそ、あらゆる分野で柔軟に仕事ができるようにならなければなりませんし、業界がいま必要としているものに適応しなければなりません。
そのため、モチベーションとコミュニケーション能力が重要なんです。関わるステークホルダーが増えたので、自分のアイデアを説明し、それを仕様書にまとめ、遠隔地にいるメンバーともコミュニケーションを取れる能力が必要です。
技術も重要ですが、意識しておきたいのは、大学で学んだ技術が社会に出る頃にはすでに古くなってしまっているかもしれないという点です。たとえば、私が最初にプログラミングしたマイクロチップのマニュアルは100ページほどでしたが、いま使っているマイクロプロセッサは4,000ページ以上もあるんですよね。そのくらい技術革新のスピードが速い。
だからこそ、新しいツールや技術を常に探して、積極的に開発プロセスに取り入れていく柔軟性が大事だと思います。「いま持っている技術」に固執するよりも、「毎日、毎年アップデートする姿勢」をもつことが重要なんです。
──ありがとうございます。最後に、次世代のエンジニアへのメッセージをいただければと思います。
「夢」を大切にしてほしいですね。私の場合は、自分が開発に携わったソフトウェアを積んだクルマが公道を走っている姿を見ると、この仕事をやっていて本当によかったと思えるんです。製品の裏側にいる人たちの思いや品質へのこだわりを知っているからこそ、心から「この製品は信頼できる」と言える。それがものづくりの醍醐味であり、エンジニアとしてのモチベーションになると思います。デンソーにはそうした夢を実現できる環境があるし、私自身が味わっている誇りと喜びを、次世代のエンジニアにもぜひ体験してほしいと思っています。
※ 記載内容は2025年6月時点のものです
- ソフトウェアエンジニア積極採用中
キャリア・生き方執筆:inquire 撮影: スタジオワーク
COMMENT
あなたが実現したいこと、学びたいこと、可能性を広げたいことに、この記事は役に立ちましたか?
ぜひ感じたことを編集部とシェアしてください。お問い合わせはこちらRELATED
- ビジョン・アイデア2022.2.14 デンソーが推進するCASE時代におけるソフトウェア改革 『自動車業界のTier1』から、『モビリティ社会のTier1』を目指して
- 技術・デザイン2024.7.5 クルマも社会とつながり、価値をアップデートし続ける時代へ SDxへの挑戦。モビリティ開発もソフトウェアファーストにシフトする
- ビジョン・アイデア2024.7.19 社会イノベーションを横断的に支える、CPSソフトウェア基盤開発チームとは?
「できてない」 を 「できる」に。
知と人が集まる場所。デンソーのオウンドメディアDRIVENBASEについて トップページを見る



