
電動化の要・パワエレ機器の進化は、カーボンニュートラルの道へとつながっている。
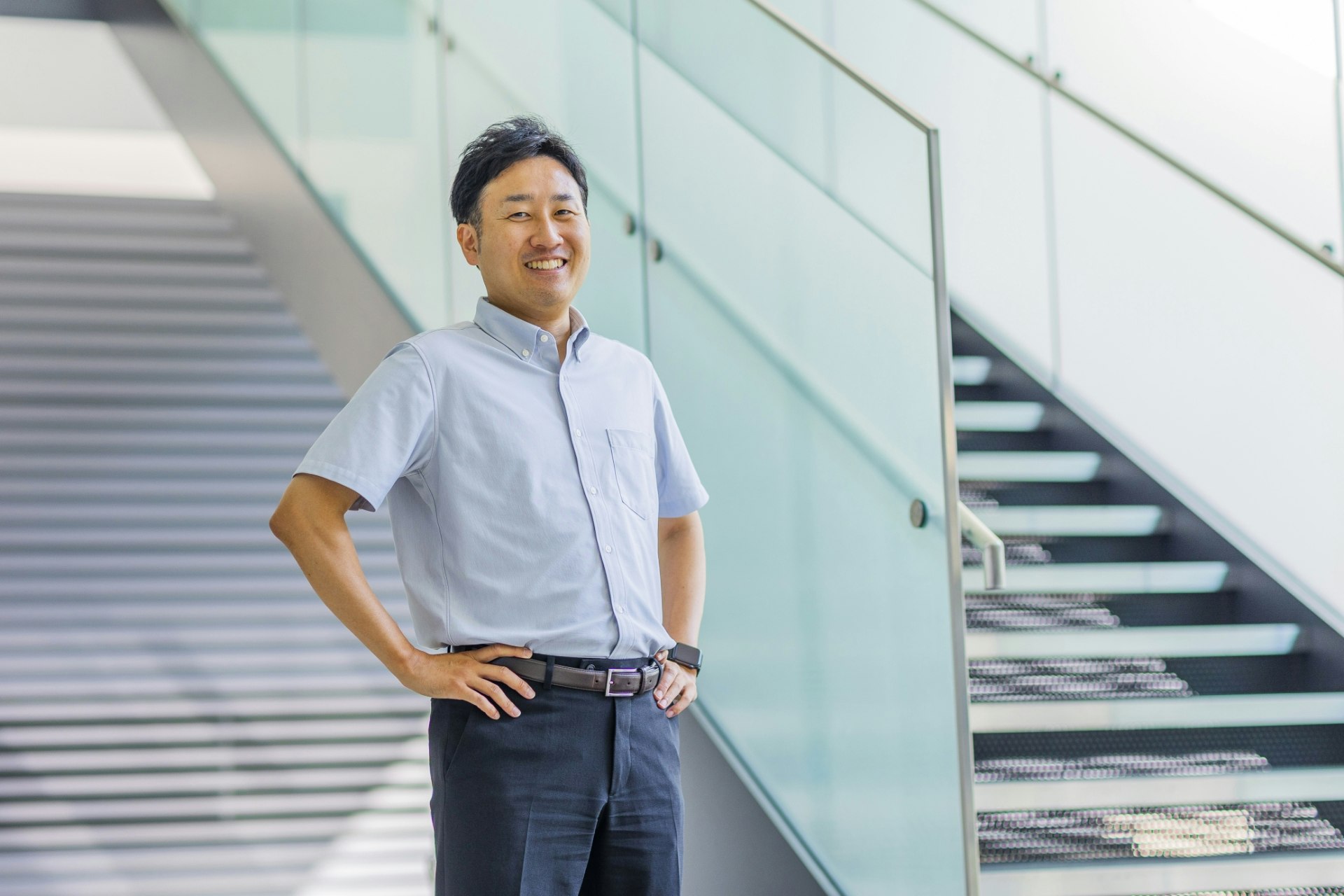
-
Target この記事の主なターゲット
-
- 技術者やエンジニア
- EV関連の研究者や開発者
- 自動車業界のプロフェッショナル
- カーボンニュートラルに関心がある一般の人々
- アイシンや自動車部品メーカーに興味がある求職者
-
Point この記事を読んで得られる知識
-
この記事から、アイシンの技術者が電気自動車(EV)のパワーエレクトロニクス機器の開発に取り組んでいる様子がわかります。特に、電力変換効率の向上や機器の小型化、信頼性の高い機器の開発が課題となっており、これらを克服することでEVの普及が進むと考えています。高効率で小型化されたパワエレ機器の開発は、車両のコストダウンにつながり、結果としてカーボンニュートラルの実現にも寄与することが期待されています。
技術者は、複数の要素技術を組み合わせてシステム全体の最適化を図ると同時に、新しい半導体など、2030年に向けた先行開発にも挑んでいます。また、研究機関やベンチャー企業との協業も進めており、これにより最先端技術の導入と開発が進められています。
さらに、製造プロセスの見直しや新材料の検討も行い、カーボンニュートラルに向けた取り組みを強化しています。この中で求められる技術者は、自律的に課題を見つけ、解決策を出し、どんな状況でも柔軟に対応できるマインドを持つ人材です。
-
Text AI要約の元文章
-
カーボンニュートラルに向けて世界が動く中、クルマの電動化が加速しています。普及の壁となっている課題を乗り越えるべく、EVに欠かせないパワエレ機器の開発に挑む技術者がここアイシンにいました。
2030年を見据えた先行開発に挑む
――EV(電気自動車)にまつわる開発をなさっているそうですが、具体的には?
T.R:私は電力変換器など、パワーエレクトロニクス(以下パワエレ)領域の機器について新商材の企画構想と先行開発を行っています。
――パワエレ機器の開発には、どのような課題があるのでしょうか?
T.R:ひとつは電力変換効率の向上。これは電費、つまり航続距離に影響しますので、非常に重要ですね。もうひとつは機器自体の大きさ。EVに欠かせない機器である上、搭載場所が限られることから、小型化も必須です。あとは厳しい環境にさらされる機器ですから、信頼性の確保も重要です。
――これら要素技術の進化がEVの進化につながると。
T.R:はい。パワエレ機器の小型高効率化は、結果として車両価格の低減につながります。これらの活動が実を結び、現行のガソリン車と同等の価格・性能になれば、EVの普及、ひいてはカーボンニュートラルの実現に一歩近づける。そういう想いで日々の仕事に取り組んでいます。
――さらにはビジネスの面でも貢献できるということですか。
T.R:もちろん。エンドユーザーの意向をしっかり捉えた開発を進めることで、幅広いメーカー・車種に対応できる優れた製品開発につながるはずですから。
――先行開発ということですが、いつまでにどれくらいといった目標はありますか?
T.R:先行開発ですから、世の中に今あるものの改善を期待されているわけではありません。2030年などの未来を見据えて「その頃にはこういう新しい半導体が量産になってくる。だから先行的にそういうものを使い、より高効率なものの開発に今チャレンジしよう」といった取り組みを要素技術ごとに行っています。
――確かに。10年後にはまったく性能の違う電池が出ているかもしれないですしね。
T.R:ええ。そうした先進的な研究を行なっている大学の研究室やベンチャーとの協業も多いですね。学会論文確認、展示会等にも参加しながら、我々のビジョンに合致するところがあれば、積極的に連携を取りに行っています。
要素技術開発と、システム全体の最適化を同時に進める
――現在はどのような業務を?
T.R:各アイテムの要素技術開発と、それら複数のアイテムを組み合わせたシステムの企画構想および組織マネジメントが、私の主な業務ですね。
――先ほど機器の小型化という話がありましたが、どれくらい小さくしようと考えていますか?
T.R:ざっくりですが、現行品の半分くらいの大きさを目指しています。もちろん詳細を詰める過程で修正は発生しますが、まずはそこを目指した時にどういう課題が出るのかというやり方で進めています。根本的な部分から見直しつつ、既存のものの延長線上にはないドラスティックなサイズダウンを目指しています。
――半分ですか!どのあたりがボトルネックになりそうですか?
T.R:電力変換効率は現在でも95%以上くらいの性能が出ていて、これ以上はなかなか難しいのですが、現状の性能を保ったまま小さくするのが難しいですね。部品が密集して熱がたまりやすくなり、どうしても性能が落ちてしまいますから。ただ、パワエレ機器単体ではなく車両システムとして開発できる環境があるので、うちはこの点で有利ではあると思います。
――システム全体で、というのはどのように?
T.R:ある程度各部品のイメージができてきたら、他の部品やユニット全体を担当する技術者と現状をすり合わせた上で「ここに冷却の水路があるから、この部品はこういう形状にして、このあたりで活用する方が全体としては効率がいいよね」といった感じで、ユニットとして最適なものをつくり込んでいくイメージです。
――なるほど。普段からこういう開発をしているということでしょうか。
T.R:ええ。例えば、我々アイシンはギアボックスとECUの一体化に20年くらい前から取り組んできました。生産技術含め、こうした機械系と電子系の一体化技術の積み重ねが、パワエレ機器と他部品のモジュール化にも役立つと考えています。
――その他の取り組みがあれば教えてください。
T.R:そうですね、今後のカーボンニュートラルを見据えた時に、「こういう要素技術ももっておかなきゃいけないんじゃないか」ということは考えていますね。
――例えば?
T.R:基板防水のために高温で炉に入れて接着剤を硬化させるという工程があるのですが、当然カーボンニュートラルを見据えるとそういう工程を減らしていかないといけませんよね。そのために、今のうちから製造プロセスの見直しや、新しい部材の検討などにも取り組んでいるわけです。
――最後に、どのような技術者の方を求めているのか教えてください。
T.R:既定路線に沿って動くのではなく、自分で行き先を決めて、自分で答えを出しに行く。それが仮に失敗しても、違う方向にすぐに動ける。そういったマインドを持った人を求めています。開発の成否だけでなく、取り組み姿勢そのものが評価される職場ですので、やりがいをもって働けるはずですよ。



