
法務が事業の推進力となるために──リスクと前進のバランス感覚を磨いていく
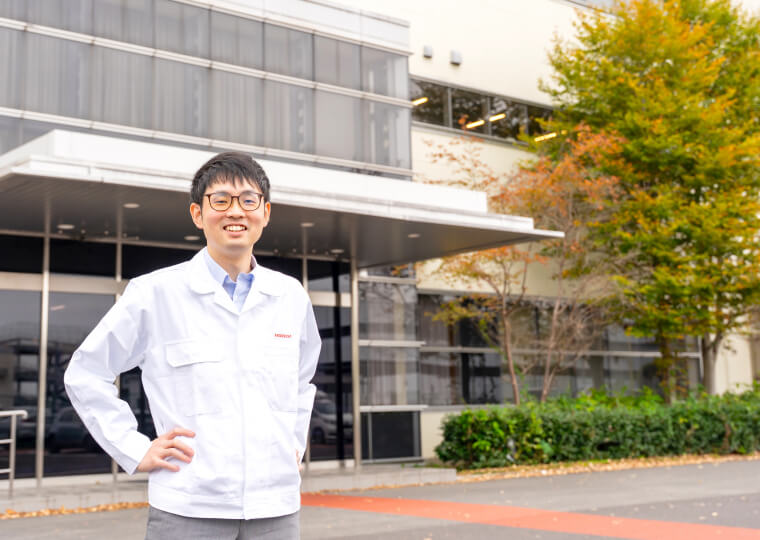
-
Target この記事の主なターゲット
-
- 法務や知財のプロフェッショナルを目指す学生や新卒社員
- 国際企業の法務部門でキャリアを築きたいプロフェッショナル
- 自動車業界での法務に関心のある人
- 企業の経営戦略に興味を持つビジネスパーソン
- Hondaや技術開発に興味のある人
-
Point この記事を読んで得られる知識
-
記事を読むと、Hondaで知財や法務業務を通じてキャリアを築いている髙見直輝の経験を知ることができます。髙見は、法学部で学んだ後、新卒でHondaに入社し、知財領域でキャリアをスタートさせました。その後、法務業務へと領域を広げ、現在ではADASプロジェクトを担当しています。彼の業務の中心は取引先企業とのライセンス契約や関連する法務対応です。
髙見は、『期待を超える法務サービスの提供』を意識し、単にリスクを指摘するだけではなく、課題解決に向けた具体的なアドバイスを提供することを目的としています。これには、Hondaが目指す方向性や事業の背景への深い理解が不可欠であると述べており、事業部門との密なコミュニケーションと信頼関係の構築が重要だと強調しています。
また、知財と法務の両方の経験を持つことで対応できる範囲が広がり、スピード感を持って事業部門からの相談や取引との契約交渉にも対応可能になるとしています。髙見は、自らの専門性を磨く一方で、広い視点で物事を見ることが必要であると感じています。具体的には、契約におけるリスクを見極めるだけでなく、経営層の視点も取り入れ、企業のビジョンの実現に寄与することが法務の役割であると再確認しています。Hondaのカルチャーにおける自由な意見交換が、彼の成長を支える要素となっています。
-
Text AI要約の元文章
-
「事業部門から信頼される法務担当者になりたい」と話す髙見。2018年に新卒で入社して以来、知財領域でキャリアを積み、現在は法務担当としてADAS(先進運転支援システム)やアライアンスのプロジェクトに携わっています。「開発や技術のサポートをしたい」という想いをモチベーションに専門性を磨いてきた髙見が、Hondaで働く魅力を語ります。
髙見 直輝Naoki Takami
コーポレート管理本部 知的財産・法務統括部 第二法務部 栃木法務課
学生時代は法学部で学び、2018年Hondaに新卒入社。二輪やパワープロダクツの技術契約を扱う部署で知財業務からキャリアをスタート。特許に関する実務やHondaが保有する知財を活用した事業創出などに従事した後、法務領域に異動。四輪事業に関する契約やアライアンス、M&Aに関する法務業務を担当している。
期待を超える法務サービスの提供がミッション。リスクの指摘にとどまらないサポートを
知財と法務に関わる領域からHondaの事業や経営を支える知的財産・法務統括部。そのなかで髙見が所属するのは、四輪事業における契約やアライアンス、M&Aなどを担当する部署です。
「私たちの業務は、開発委託、共同研究、部品の購買に関する契約といったお取引先との契約書レビューから、Hondaの事業を企画する際に法的な観点から関わる戦略的なプロジェクト支援まで、多岐にわたります」
現在、髙見が担当しているのは、ADASのプロジェクト。取引先企業とのライセンス契約を中心に、関連するすべての法務対応を一手に引き受けています。モビリティ業界のなかでも比較的新しい領域ということもあり、「事業を前に進めるためのサポート」がとくに重要だと話します。
「法務担当者として心がけるべきは、『期待を超える法務サービスの提供』です。たとえば、契約書のレビューをする際に『ここにリスクがあります』と指摘しても、事業部門としては『リスクがあるのはわかった。では、どうすればいいのか?』となりますよね。法的なリスクを伝えるだけではなく、一歩踏み込んで『どうしたらその課題を解決して事業を前に進めることができるか』というアドバイスやサポートを行うことを意識しています」
そのためには、Hondaとしてめざす方向性や事業の背景への深い理解が不可欠だと続けます。
「リスクを指摘するだけなら、社外の専門家に相談すればいい。私たちが法務として付加価値を出していくためには、経営層や事業部門が描いているビジョンを把握することはもちろん、事業部門のメンバーとの信頼関係の構築がとても重要です。
一緒にプロジェクトを進めるメンバーと密にコミュニケーションをとりながら事業の背景を理解することで、適切な提案ができます。『法務に相談すればしっかりサポートしてもらえる』という信頼関係が大事だと思っています」
開発や技術のサポートがしたい。知財から法務へと領域を広げながら経験を積む
髙見は、2018年に新卒で Honda に入社。学生時代は法学部で学び、メーカーに勤務していた父親の影響もあり、製造業の企業を中心に就職活動をしていたと言います。そこには、その後のキャリアの軸となる想いがありました。
「日本の高い技術力で世界と戦えるような企業で働きたいと思っていたんです。文系ではあるものの、開発や技術のサポートができる仕事がしたいという想いがあり、自分の想いを実現できる会社を志望していました」
数ある技術力の高いメーカーのなかで Honda を選んだのは、事業領域の広さとHondaが掲げる夢への共感でした。
「四輪だけではなく、二輪、パワープロダクツ、さらには航空機やロボットと幅広い事業を展開していて、とても技術力がある会社だと感じたんです。そこに無限の可能性を感じてワクワクしました。選考過程で出会う社員たちも夢を語ってくれる人が多く、Honda ならロボットと人間が共存する社会や交通事故死者ゼロの実現という壮大な夢のような話も実現できるんじゃないかと感じたのです」
入社後、研修を経て配属されたのは、二輪やパワープロダクツの技術契約を扱う部署でした。
「就職活動期間や研修期間にさまざまな仕事を知るなかで、知財なら技術により近いところでサポートできるのではないかと考えて希望しました。運よく希望通りの配属がかない、お取引先との秘密保持契約書から仕事を覚えていきました。
その後、組織変更などもあり、特許出願に関わる実務と契約まわりの業務の両方を担当するようになりました。開発者とのヒアリングを重ねることで発明を出願したり、他社の特許権を侵害していないか調査をしたりと、苦労はありましたが、文系でありながらも深く技術に関わることができました。
また、当時の部署でHondaが保有している知財を活用した新規事業を企画するというプロジェクトが立ち上がり、私も参画することに。実際にお客様にサービスを提供することができ、自分たちで事業を企画した経験は今に活きています」
そして、2023年に組織変更により知的財産部門と法務部門が統合されたことを機に、法務領域に挑戦します。
「知財と法務の両方の知見があれば、ひとりで対応できる範囲が広がって、事業部門から相談を受けた時やお取引との契約交渉が発生した時などにもスピード感を持って対応できます。知財に特化することで知財領域の専門性は高まっていきますが、法務領域も経験したいという気持ちはずっとありました」
大きな視点から考えることで、ビジョンを実現できる契約条件が検討できる
これまでのキャリアで、複数回の部門再編を経験してきた髙見。その都度、業務領域が広がっていったことが、大変ながらも自身の成長につながったと振り返ります。
「新しい業務が加わった当初は、何もわからない状態からのスタート。諦めずにコツコツ勉強してきました。知財に関しては必死に特許法などの勉強をしましたし、技術に関することは、開発者をはじめいろいろな人に話を聞きにいき、実物を見て学んでいきました。
技術者と同じように、私たちも現場・現物を見ることはとても大切です。図面だけ見ていては想像できないことも、現物を見ることで理解できることがあるんです」
また、法務領域に移ってから経験したグループ会社の再編といったプロジェクトも、視野を大きく広げるきっかけになったと言います。
「経営に大きく関わることですから、折りに触れて経営層への提案や報告などを経験する機会があり、そこで学ぶこともたくさんありました。
たとえば、私たちは契約におけるリスクを洗い出すことも仕事ですから、どうしても契約書の条項などの細かい部分に目線がいってしまうのですが、経営層が求める情報は『会社のビジョンが実現できるかどうか』です。目の前のことにとらわれず、大きな視点で見た時にどういった契約条件に持っていくのがいいのかを考える必要性を実感しましたし、事業部門と連携しながら、その事業がめざすものの実現に向けて法務支援を提供することが法務の役割なのだとあらためて学びました」
現在担当するADAS分野も、新たな挑戦。「未完」の分野だからこその難しさに直面していると話します。
「関係部門が多いことに加えて、スピード感が求められます。契約の交渉と同時並行でさまざまな部門との調整や法的な課題解決をしていかなければいけません。自動運転やADAS分野は技術の進歩に対して法律が追いついていない部分も多くあるため、今ある材料のなかで最適解を出さなければいけないのです。さらに、世界各国の法令基準に合わせていく必要があります。
そういった難しさに毎日直面していますが、『お客様により良い商品を届ける』を判断の軸としながら、世界中の法務メンバーと協力しながら進めています」
難しいからこそ得られるものも多い。議論を交わせる環境でめざす「頼れる法務」
さまざまな困難を乗り越えながら成長してきた髙見は、そのモチベーションの源泉について、こう語ります。
「難しいからこそ、専門性や経験値など、そこで得られるものが大きいと感じています。何より、事業に貢献できて、素晴らしい製品をお客様に届けることができる。入社の理由だった『開発や技術のサポートができる仕事がしたい』という想いをかなえることができています。
そして、自分の関わった案件がニュースになり、世の中で話題になっている。それを見られることも大きな喜びです」
さらに、立場に関係なく意見を言い合えるHondaのカルチャーも、自身の成長につながってきたと続けます。
「ワイガヤをはじめ、それぞれの考えをぶつけ合える場所があるので、相談しやすいんです。自分の意見を言いにくい空気はまったくありませんし、個々の案件についてはもちろん、部署としての方向性などについても、さまざまな議論が交わされている。課題に対してどう対策していくかを皆で考えることができる健全さを感じています」
そんな環境のなかで目標とするのは、より幅広い領域に対応できる法務のスペシャリストです。
「これまでは、研究開発に関わる経験が多かったので、研究開発領域以外の法務領域やガバナンス、訴訟などの経験も積みながら、幅広く法務領域に対応できる人材になっていきたいと思っています。
事業部門から信頼してもらうためには、知識は豊富だけれどリスクしか教えてくれないというのではいけません。リスク予防と事業推進のバランス感覚を持ちながらサポートできる存在になりたいですね」
変わらぬ想いをモチベーションに、広く深い専門性を身につけながら、事業の推進力となることをめざします。
※ 記載内容は2025年10月時点のものです



