大槻 幸夫
サイボウズ株式会社 コーポレートブランディング部長 チームワークスタイルエバンジェリスト
この人が書いた記事をもっと読む

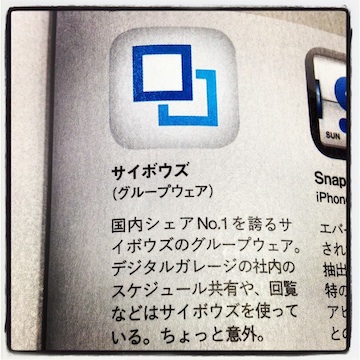


この記事を通じて読者は、サイボウズが自社メディア『サイボウズ式』を立ち上げた理由とその背景を知ることができます。編集長である大槻さんが雑誌記事を通して感じた、サイボウズが意外と受け取られている現状に対して、世の中のコラボレーションツールの現状を自身の目で確かめたいという動機があります。
また、メディア立ち上げの際に彼が社長の青野氏に相談をし、承認を得て実現に至ったプロセスが描かれています。このメディアの目的は、コラボレーションとITに関する記事を提供し、特にビジネスチームによる新しい価値創出に役立つ情報を伝えることにあり、個人向けやコンシューマー向けの情報とは一線を画しています。
さらに、このプロジェクトを通じて読者に自分たちも読みたいと思うような記事を提供し、サイボウズを紹介する機会ともしていく意図が述べられています。これは、新しい価値を目指すチームのための情報源として、読者が仕事で活用できる内容を提供することを目指しています。

はじめまして。
「サイボウズ式」の編集長を務めます、大槻です。
先日、とある雑誌を購入して読んでいたときのことです。
冒頭特集の中で「サイボウズ」をご紹介いただいていたのですが、その脇に添えられていた文章に目がとまりました。
「国内シェアNo.1を誇るサイボウズのグループウェア。
デジタルガレージの社内のスケジュール共有や、回覧などはサイボウズを使っている。
ちょっと意外。」
「ちょっと意外。」
・・・・意外?
長年サイボウズで働いてきた私にとっては、むしろ「意外」という記述が出てくることに「意外」でした。。
「シェアNo.1の」と書かれている以上、サイボウズがそれほどマニアックなツールではないことはご存じ頂けているようですが、でも 「意外」 という表現。
視線を窓の外に移し、ふと思うと、この雑誌は先進的なWebサービスやスマホ、タブレットといったツールを使いこなして仕事をされている方々を取材されていることに気づきます。
そこから感じる、
「Googleカレンダー、Facebook、Twitter、Dropbox、Evernote、Gmail、Skype、LINE・・・これだけ便利なツールが世に溢れているのに、なんでいまさら、サイボウズなんか使ってるの?」
という、この記事を書かれたライターさんの言外の声。
やはりそうか・・・と。
正直なところ、ここ数年、ソーシャルメディア上での会話や勉強会、各種イベントを通じて色々な方の声を聞いてきて感じたことと合致するのです。
考えてみればごく当たり前のことです。
コラボレーションツールとしてサイボウズ製品が真っ先に頭に上がるのは、サイボウズ社員ぐらいなのですから・・
そこで一度、「サイボウズ製品」から離れて、世の中のコラボレーションはいま、一体どうなっているのかを探ってみたいという欲求に駆られました。
「クラウド」「ソーシャル」「スマートフォン」「タブレット」・・・様々な技術革新を受けて、ITを使ったコラボレーションが、今どう変化してきているのか、純粋にこの目で確かめたいと思いました。
そんな話を社長の青野に相談してみました。
メディアをやってみたいと。
「いや・・大槻さんはサイボウズのプロモーション担当なんだから、やって欲しいことはそういうことじゃない」
という反応を覚悟の上で。
ところが、青野からは
「おもしろそうじゃん!やってみたら?」
と即答してもらえました。
ということで、OKをもらってから5週間ぐらいで立ち上げにこぎ着けたのがこちらのサイトになります。
編集長という特権(?)を生かして、色々なところに取材に行きたいと思います。
「私が知りたい」が基準です。自分たちで読んでみたい記事を作りたい。
これまで色々なIT関連の情報を見てきましたが、どちらかというと「個人向け」あるいは「コンシューマー向け」の「ツール」を中心とした情報が多かったのではないか、と感じています。あるいは「オフィス」という箱物についての情報。
「チーム」による「ビジネス」「コラボレーション」という軸での情報は少なかったのではないか、と思いました。
そこで、このサイトのコンセプトは「新しい価値を生み出すチームのための、コラボレーションとITの情報サイト」としました。
他のメンバーと一緒に仕事をするときに参考になる情報と、ときどき「サイボウズ」についてお伝えするメディアに育てていければと思います。
ではどうぞ、よろしくお願いします。
SNSシェア
サイボウズ株式会社 コーポレートブランディング部長 チームワークスタイルエバンジェリスト
この人が書いた記事をもっと読む